2021年12月の #ミチョランマ 消化 ― 2021/12/31 15:07:00
*32枚目
ショパン:ポロネーズ集
サンソン・フランソワ
恥ずかしながら3カ月ぶりミチョランマ消化。
フランソワのショパン、ソナタ2、3番と名演集は昔から好きなので他のも聴きたくて箱買いしたやつ。
いつ買ったか知らんけど(多分ブログ掘ったら分かる)。
フランソワのショパン、「感興のおもむくまま」なんだけど決して野放図でないところが素敵。センスの塊。
名前付きの「軍隊」「英雄」以外の方がむしろその良さが出ている気がする。
*33、34枚目
ヘンデル:オラトリオ「メサイア」
レナード・バーンスタイン/NYPほか
恥ずかしながら全曲版聴くの初めて。
とはいえこれってだいぶレニーの手が入ってて曲順入れ替えやらカットやらしてるんだけど。
そのお陰か全く退屈せず一気に聴かせる。
冒頭の序曲やハレルヤコーラスはかなり重いけど、2部(謝肉祭パート)の終盤の盛り上がりが凄くて、多分それゆえの設定なのかなー。
*35枚目
ショパン:ポロネーズ集(遺作)
同:幻想曲
同:タランテラ
同:舟歌
同:ロンド(2つのピアノのための)
サンソン・フランソワ
ショパンの2台のピアノのためのロンドって多分初めて聴いたと思う。
めっちゃいい。
何と言うか良い意味で単純かつ華やか。
爽快!
2021年9月の #ミチョランマ 消化 ― 2021/11/01 14:48:30
*29枚目
フランク:ヴァイオリンソナタイ長調
ショーソン:ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のためのコンセールニ長調op.21
ジャック・ティボー
アルフレッド・コルトー
with string quartet
フランクの名盤として誉れ高いこの演奏、恥ずかしながら聴いてなかった。
とにかく凄かった!
蕩けるようなポルタメント。
たゆたう囁きから凛とした響きまでの振り幅。
特に偶数楽章が素晴らしい。
アゴーギクの巧みさは魔法。
熱を帯びたコルトーのミスタッチが所々あるが、それさえ魅惑的。
*30枚目
Echoes Of Life エコーズ・オヴ・ライフ
アリス=紗良・オット
イン・ザ・ビギニング・ワズ
トリスターノ:イン・ザ・ビギニング・ワズ
ショパン:24の前奏曲 作品28 第1番ハ長調、第2番イ短調、第3番ト長調、第4番ホ短調
インファント・レベリオン
リゲティ:ムジカ・リチェルカータ 第1曲
ショパン:24の前奏曲 作品28 第5番ニ長調、第6番ロ短調、第7番イ長調、第8番嬰ヘ短調、第9番ホ長調
ウェン・ザ・グラス・ワズ・グリーナー
ニーノ・ロータ:ワルツ
ショパン:24の前奏曲 作品28 第10番嬰ハ短調、第11番ロ長調、第12番嬰ト短調、第13番嬰へ長調、第14番変ホ短調、第15番変ニ長調《雨だれ》
ノー・ロードマップ・トゥ・アダルトフッド
ゴンザレス:前奏曲 嬰ハ長調
ショパン:24の前奏曲 作品28 第16番変ロ短調、第17番変イ長調、第18番ヘ短調
アイデンティティ
武満徹:リタニ -マイケル・ヴァイナーの追憶に- 第1曲
フレデリック・ショパン:24の前奏曲 作品28 第19番変ホ長調、第20番ハ短調
ア・パス・トゥ・ウェア
ペルト:アリーナのために
ショパン:24の前奏曲 作品28 第21番変ロ長調、第22番ト短調、第23番ヘ長調、第24番ニ短調
ララバイ・トゥ・エターニティ
オット:ララバイ・トゥ・エターニティ ― モーツァルトのレクイエム ニ短調 K.626から ラクリモーサの断片による
ショパンのプレリュード全曲に現代曲を挟み込んだアリスのコンセプトアルバム。
正直聴く前は「以前のショパン・プロジェクトみたいに微妙ちゃうか(苦笑)」なんて思ってた。
豈図らんや……すごく良い!
冒頭/狭間/ラストに置かれている各曲にすごく「意味」がある。
特に冒頭の「イン・ザ・ビギニング・ワズ」とラスト「ララバイ・トゥ・エターニティ 」。
もちろん本チャンのプレリュードもなかなかの演奏。
清冽な印象を残した彼女のワルツ集ほどではないけれど、純粋にショパンのプレリュード集としても良盤。
*31枚目
・G.ガブリエリ:第9旋法による12声のためのカンツォーナ
・S.シャイト:コルネット・カンツォーナ・G.ガブリエリ:第9旋法による12声のためのカンツォーナ
・H.パーセル:《アブデラザール》からの組曲
・O.ディ・ラッソ:その者に祝福あれ(2声から12声のための)
・G.F.ヘンデル:シバの女王の入城
.・J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 第3番BWV1048
・H.W.ヘンツェ:8本の金管楽器のためのソナタ
・W.D.ジーベルト:金管楽器のロンドーベルリン・ブラス・アンサンブル

2021年5月の #ミチョランマ 消化 ― 2021/06/30 00:34:38
個人的に「翌月に前月の『#ミチョランマ 消化』を書く」をルールにしているのだけど。
今回ぎりぎりですな……(苦笑)。
*20枚目
テレマン:協奏曲集
ヘンデル:水上の音楽
ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団
テレマンはオールドスタイルではあるけど、明晰でパキパキとした好演。
さすがはフィラ管の凄腕ソロイストたち!
まさに面目躍如、といった感。
水上の音楽は、オーマンデイとハリスの2種類の編曲を収録。
こちらもオールドスタイルだからやむを得ないのだけど、それにしてももっさりというか腰が重い。
どちらかと言えばオーマンディアレンジの方が好み。
*21枚目
ストラヴィンスキー:ペトルーシュカからの3楽章
プロコフィエフ:ピアノソナタ 第7番
ヴェーベルン:ピアノのための変奏曲
ブーレーズ:第2ソナタ
マウリッツォ・ポリーニ
言わずと知れた名盤。 ペトルーシュカはやっぱりすごい!
汗ひとつかかず軽やかに、オケと同じくらいの(いや、越えている?)情報量が迸る。
ポリーニは正直好きな演奏家ではないけれど、これとさすらい人幻想曲はホント圧倒される。
そして個人的にはプロコフィエフって苦手だけど、この演奏だとすんなり受け付けられる。
てか、7番の終楽章はやっぱりぶち上がる!
ヴェーベルンはさておき、ブーレーズの曲はまだまだ私には消化できません(苦笑)。
ちょっと5月はおサボり気味だったと反省(実は6月もなんだけど)。
年内100枚消化、厳しくなってきたなぁ(汗)。
1+235本のトランペット。 ― 2010/09/07 03:34:26
久しぶりにコンサートを聴きに行った。
後輩が出演しているので。
サントリーホールも何年ぶりだろう。
なんと最大236本ものトランペットが鳴り響くというチャリティーコンサート。
詳しくはこちら。↓
http://www.aarjapan.gr.jp/activity/report/2010/0906_397.html
*のついている曲が全員演奏で、あとはプロの演奏なのだけど、さすがに全員演奏は圧巻。
ものすごい音圧で、終演後はお腹空いたもん。(笑。
最初こそ、やっぱり「ズレ」みたいなものを感じたのだけど、曲を重ねるにつれて息が合っていくからすごい。
どんなモンでも「やりきる」事ってすごいよね、て感じさせられるプログラムでした。
なお、2部のオルガン即興演奏は童謡「赤とんぼ」をモティーフにしたもの。
これがもう感動したのなんのって……。
主題の発展、変容、展開。
やはり音楽の根っこは「インプロビゼーション」にあるのだ、ということをまざまざと見せ付けられた。
おまけ。
秋篠宮ご夫妻臨席に驚く。
リック・オービエ(トランペット)
ティエリー・エスケッシュ(オルガン)
菅原 淳(ティンパニ)
【プログラム】
モンテヴェルディ:歌劇「オルフェオ」よりファンファーレ*
ブラント:コンサートピース第2番
シャルパンティエ:テ・デウムより「プレリュード」*
クラーク:トランペット・ヴォランタリー*
ムレ:交響的ファンファーレ*
パジーニ:カンタービレ
シューベルト:ワインと愛
エスケッシュ:舞踏的幻想曲
ベーメ:協奏曲へ短調より第1楽章
エスケッシュ:トランペット・ストーリー
松下功:「祈りのファンファーレ」
ビゼー:アニュス・デイ
オルガン即興演奏
エスケッシュ:クリスマス・メドレー
ヴェルディ:歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲*
ベートーヴェン:交響曲第9番より「歓喜の歌*
ヘンデル:メサイヤより「ハレルヤ」*
ヴァンベスレール:ベスト・オブ・フランス*
後輩が出演しているので。
サントリーホールも何年ぶりだろう。
なんと最大236本ものトランペットが鳴り響くというチャリティーコンサート。
詳しくはこちら。↓
http://www.aarjapan.gr.jp/activity/report/2010/0906_397.html
*のついている曲が全員演奏で、あとはプロの演奏なのだけど、さすがに全員演奏は圧巻。
ものすごい音圧で、終演後はお腹空いたもん。(笑。
最初こそ、やっぱり「ズレ」みたいなものを感じたのだけど、曲を重ねるにつれて息が合っていくからすごい。
どんなモンでも「やりきる」事ってすごいよね、て感じさせられるプログラムでした。
なお、2部のオルガン即興演奏は童謡「赤とんぼ」をモティーフにしたもの。
これがもう感動したのなんのって……。
主題の発展、変容、展開。
やはり音楽の根っこは「インプロビゼーション」にあるのだ、ということをまざまざと見せ付けられた。
おまけ。
秋篠宮ご夫妻臨席に驚く。
リック・オービエ(トランペット)
ティエリー・エスケッシュ(オルガン)
菅原 淳(ティンパニ)
【プログラム】
モンテヴェルディ:歌劇「オルフェオ」よりファンファーレ*
ブラント:コンサートピース第2番
シャルパンティエ:テ・デウムより「プレリュード」*
クラーク:トランペット・ヴォランタリー*
ムレ:交響的ファンファーレ*
パジーニ:カンタービレ
シューベルト:ワインと愛
エスケッシュ:舞踏的幻想曲
ベーメ:協奏曲へ短調より第1楽章
エスケッシュ:トランペット・ストーリー
松下功:「祈りのファンファーレ」
ビゼー:アニュス・デイ
オルガン即興演奏
エスケッシュ:クリスマス・メドレー
ヴェルディ:歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲*
ベートーヴェン:交響曲第9番より「歓喜の歌*
ヘンデル:メサイヤより「ハレルヤ」*
ヴァンベスレール:ベスト・オブ・フランス*
通勤ミュージック~090127 ― 2009/01/27 16:33:43
*ストコフスキー・スペキュタクラー
RCA 2 in 1シリーズ。まずは1枚目から。
1.無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番~プレリュード(バッハ~ストコフスキー編)
2. 同第2番~シャコンヌ(同~同)
3. 管弦楽組曲第3番~アリア(同~同)
4. 小フーガ ト短調(同~同)
5. 組曲「水上の音楽」(ヘンデル)
6. 同「王宮の花火の音楽」(同)
バッハはLSO、ヘンデルはRCAビクター響。
もうプレリュードから(いい意味で)映画音楽のノリ。
今ならさしずめゲーム音楽か。(笑
楽しく明るく歌ってルンルン。
それがシャコンヌで一変。
あたかも愁嘆場を演じるかのような大げさな身振りの中に、甘美な色気がムンムンと香り立つ。
先日のイエペスのように、内へ内へと向かうような内省的な空気とは全く違って、放射されるエネルギーに満ちているが、これはこれで(バッハが求めているものとは違ったとしても)極められた「何か」が心に響いてくる。
もちろん「好き嫌い」という概念は否定しないし、音楽を楽しむ上で重要な様子だとは思うが、結局のところ、その「何か」を伝え切れているか、が自分の中では大きな評価基準のような気がする。
「彼(=バッハ)が私の編曲をどう思うか。それは私の死後の運命がどうなるか分からないけど、とにかく行った先で彼に会ってみないことには何とも言えない」(by ストコフスキー)
コッテリと歌い抜くG線上のアリア。
ド派手な金管のトリルで飾られる小フーガ。
とにかく、やり切ろうとする信念の説得力に脱帽!
ストコフスキーのバッハは、チョコフィルのライヴ盤を持っていて、あれも凄い(特に「パッサカリアとフーガ」)。
ただ選曲は当音盤の方がバラエティーに富んでいていいかな。
ヘンデルの2曲も十二分に楽しませてくれる。
クーベリック盤のような「威容」こそないけれど(ていうか、そんなもの眼中にない?)、とにかく大らか。
「水上の音楽」では、最初から最後まで、これでもかと言うくらいにメロディーに合わせてスネアドラムを鳴らしまくる。
やっぱり、というか期待通り、というか。
ところが一転「花火」では意外なほど穏やかな表情を見せる。
テンポも全体に落ち着いてゆったり。
もちろん楽器は補強してるけど、序曲で不意に見せる弱音にも驚かされる。
「歓喜」も開始の弦でぐっと抑え、繰り返す度にジワジワと盛り上げる。
しかし最後の金管でもド派手にはならない。むしろ大人。
……やるとしたら、普通逆(水上=穏やか 花火=派手)だよね。(苦笑
その辺の一筋縄では行かないところもまた、「ストコ節」たるゆえんか。
RCA 2 in 1シリーズ。まずは1枚目から。
1.無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番~プレリュード(バッハ~ストコフスキー編)
2. 同第2番~シャコンヌ(同~同)
3. 管弦楽組曲第3番~アリア(同~同)
4. 小フーガ ト短調(同~同)
5. 組曲「水上の音楽」(ヘンデル)
6. 同「王宮の花火の音楽」(同)
バッハはLSO、ヘンデルはRCAビクター響。
もうプレリュードから(いい意味で)映画音楽のノリ。
今ならさしずめゲーム音楽か。(笑
楽しく明るく歌ってルンルン。
それがシャコンヌで一変。
あたかも愁嘆場を演じるかのような大げさな身振りの中に、甘美な色気がムンムンと香り立つ。
先日のイエペスのように、内へ内へと向かうような内省的な空気とは全く違って、放射されるエネルギーに満ちているが、これはこれで(バッハが求めているものとは違ったとしても)極められた「何か」が心に響いてくる。
もちろん「好き嫌い」という概念は否定しないし、音楽を楽しむ上で重要な様子だとは思うが、結局のところ、その「何か」を伝え切れているか、が自分の中では大きな評価基準のような気がする。
「彼(=バッハ)が私の編曲をどう思うか。それは私の死後の運命がどうなるか分からないけど、とにかく行った先で彼に会ってみないことには何とも言えない」(by ストコフスキー)
コッテリと歌い抜くG線上のアリア。
ド派手な金管のトリルで飾られる小フーガ。
とにかく、やり切ろうとする信念の説得力に脱帽!
ストコフスキーのバッハは、チョコフィルのライヴ盤を持っていて、あれも凄い(特に「パッサカリアとフーガ」)。
ただ選曲は当音盤の方がバラエティーに富んでいていいかな。
ヘンデルの2曲も十二分に楽しませてくれる。
クーベリック盤のような「威容」こそないけれど(ていうか、そんなもの眼中にない?)、とにかく大らか。
「水上の音楽」では、最初から最後まで、これでもかと言うくらいにメロディーに合わせてスネアドラムを鳴らしまくる。
やっぱり、というか期待通り、というか。
ところが一転「花火」では意外なほど穏やかな表情を見せる。
テンポも全体に落ち着いてゆったり。
もちろん楽器は補強してるけど、序曲で不意に見せる弱音にも驚かされる。
「歓喜」も開始の弦でぐっと抑え、繰り返す度にジワジワと盛り上げる。
しかし最後の金管でもド派手にはならない。むしろ大人。
……やるとしたら、普通逆(水上=穏やか 花火=派手)だよね。(苦笑
その辺の一筋縄では行かないところもまた、「ストコ節」たるゆえんか。


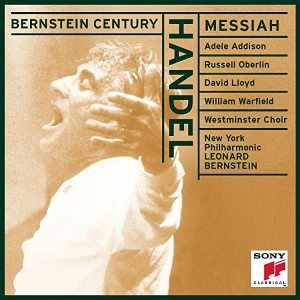
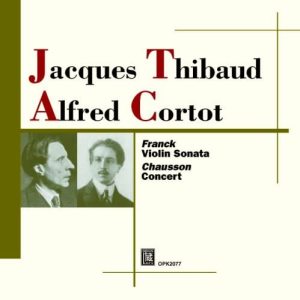



最近のコメント