マーチでアゲアゲ。 ― 2010/04/02 00:32:14
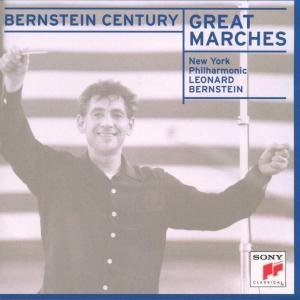
*グレート・マーチズ(バーンスタイン/NYP)
新年度、さらには転勤に伴う新生活ということで、一発気合を入れるために、未聴CDの消化ではなく、敢えてこの1枚。
先日までの寒さが嘘のように、暑いくらいの今日の東京。
その「暑さ」に引けを取らぬレニーの「熱さ」。
さんざ自分が中学校の頃に吹奏楽団でやったスーザの行進曲や「錨を上げて」が、イケイケドンドンでぶっ放される。
特に「星条旗よ永遠なれ」。
こんなに刺激的だったっけ??(笑
いわゆる“クラシカルな”楽曲でもそのスタイルは変わらない。
「3つのオレンジへの恋」のピリピリするようなテンション。
「ルール・ブリタニア」とか「ルイ・マルセイユーズ」みたいな短い曲だと、なおさらその勢いが痛快。
当時のレニーのいわゆる「録って出し」が間違いなくプラスの方向に働いてる。
アイーダの、屈託のない(無さすぎる??)音抜けの良さ。
オペラのワンシーンなのではなく、あくまでも一つの行進曲として立ってる。
後半のテンポ上がるとこのドキドキ感!
最初からむやみに熱い「酋長の行進」。
じっくり盛り上げる? 何それ?て感じ。(笑
抑え切れぬ熱気が奔流となって、終結に向かってなだれ込む。
なんてクドい見栄きりと、その後の加速!!
もう、どうしてくれるんだ。
出勤前に必要以上のアドレナリン出ちゃったじゃないか。(苦笑
久しぶりに聴いたけど、やっぱレニーの美徳ってこういうことだと思うよ。
新年度、さらには転勤に伴う新生活ということで、一発気合を入れるために、未聴CDの消化ではなく、敢えてこの1枚。
先日までの寒さが嘘のように、暑いくらいの今日の東京。
その「暑さ」に引けを取らぬレニーの「熱さ」。
さんざ自分が中学校の頃に吹奏楽団でやったスーザの行進曲や「錨を上げて」が、イケイケドンドンでぶっ放される。
特に「星条旗よ永遠なれ」。
こんなに刺激的だったっけ??(笑
いわゆる“クラシカルな”楽曲でもそのスタイルは変わらない。
「3つのオレンジへの恋」のピリピリするようなテンション。
「ルール・ブリタニア」とか「ルイ・マルセイユーズ」みたいな短い曲だと、なおさらその勢いが痛快。
当時のレニーのいわゆる「録って出し」が間違いなくプラスの方向に働いてる。
アイーダの、屈託のない(無さすぎる??)音抜けの良さ。
オペラのワンシーンなのではなく、あくまでも一つの行進曲として立ってる。
後半のテンポ上がるとこのドキドキ感!
最初からむやみに熱い「酋長の行進」。
じっくり盛り上げる? 何それ?て感じ。(笑
抑え切れぬ熱気が奔流となって、終結に向かってなだれ込む。
なんてクドい見栄きりと、その後の加速!!
もう、どうしてくれるんだ。
出勤前に必要以上のアドレナリン出ちゃったじゃないか。(苦笑
久しぶりに聴いたけど、やっぱレニーの美徳ってこういうことだと思うよ。
やっぱりすごいマタチッチ。 ― 2010/03/14 15:34:57

*ワーグナー:楽劇「神々のたそがれ」組曲(マタチッチ/チェコpo.)、楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲、歌劇「さまよえるオランダ人」序曲、楽劇「トリスタンとイゾルデ」 第1幕への前奏曲(以上、コンヴィチュニー/チェコpo.)
確かこの音盤、最初にリリースされた時はマタチッチの演奏だけだったはず。
CD1枚に30分弱だから贅沢だよな。(もったいない??
その後、コンヴィチュニーの演奏をフィルアップで入れて再リリース。
マタチッチは、N響のライヴ盤(Altus)があまりに圧倒的だったので、正直セッション録音の当盤にはあまり期待していなかった。
あの熱気、大河のような揺らぎ、「うた」……スタジオでは達成できないと思うので。
しかし、いい意味でその不安は裏切られた。
もちろんテンションや熱気はライヴ盤のほうが上。
しかしセッション録音は、香気というか艶やかさで優る。
それはチェコフィルの力かもしれないけど、特に木管のうっとりするような響き。
「ラインの旅」の冒頭で繰り返し奏される愛のテーマ。
cl.の旋回音形が、幸せな空気を醸し出す。
……これが2人(ブリュンヒルデ&ジークフリート)の最後の別れなのだとしても。(だからこそ??
「熱気はライヴ盤が上」とは書いたけど、当音盤だって十分に熱い。
セッションながら、ブラスが落ち気味なのに録り直しをしていないことからもそれが分かる。
さらにぶっちゃけ、オケの基礎体力、というか底力は明らかにN響より上だから、その意味でもじっくりと腰の据わった音楽が聴ける。
ただ残念なのはAltus盤にあった「ジークフリートの死」がないこと。
フィルアップのコンヴィチュニーは、マタチッチと比べると正直物足りない。
「マイスタージンガー」の集結部や「オランダ人」の中間部で見せる見栄切りなどに、「いかにも」なコクを感じさせる一面もあるのだけど、全体的に生真面目すぎな印象が強い。
やっぱワーグナーは“清濁併せ呑む”豪快さが欲しい、と思う。
確かこの音盤、最初にリリースされた時はマタチッチの演奏だけだったはず。
CD1枚に30分弱だから贅沢だよな。(もったいない??
その後、コンヴィチュニーの演奏をフィルアップで入れて再リリース。
マタチッチは、N響のライヴ盤(Altus)があまりに圧倒的だったので、正直セッション録音の当盤にはあまり期待していなかった。
あの熱気、大河のような揺らぎ、「うた」……スタジオでは達成できないと思うので。
しかし、いい意味でその不安は裏切られた。
もちろんテンションや熱気はライヴ盤のほうが上。
しかしセッション録音は、香気というか艶やかさで優る。
それはチェコフィルの力かもしれないけど、特に木管のうっとりするような響き。
「ラインの旅」の冒頭で繰り返し奏される愛のテーマ。
cl.の旋回音形が、幸せな空気を醸し出す。
……これが2人(ブリュンヒルデ&ジークフリート)の最後の別れなのだとしても。(だからこそ??
「熱気はライヴ盤が上」とは書いたけど、当音盤だって十分に熱い。
セッションながら、ブラスが落ち気味なのに録り直しをしていないことからもそれが分かる。
さらにぶっちゃけ、オケの基礎体力、というか底力は明らかにN響より上だから、その意味でもじっくりと腰の据わった音楽が聴ける。
ただ残念なのはAltus盤にあった「ジークフリートの死」がないこと。
フィルアップのコンヴィチュニーは、マタチッチと比べると正直物足りない。
「マイスタージンガー」の集結部や「オランダ人」の中間部で見せる見栄切りなどに、「いかにも」なコクを感じさせる一面もあるのだけど、全体的に生真面目すぎな印象が強い。
やっぱワーグナーは“清濁併せ呑む”豪快さが欲しい、と思う。
通勤ミュージック~091104 ― 2009/11/04 18:36:12
*ロッシーニ:歌劇「セビリアの理髪師」序曲、バーンスタイン:「キャンディード」序曲、ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲、ブラームス:大学祝典序曲(以上バーンスタイン/ボストン・ポップス)、マーラー:交響曲第10番1楽章(バーンスタイン/VPO)
CD-Rの青盤。
最後の1曲以外は、本来ボストン・ポップスの自主製作盤で出ているもの。
現物が欲しいのだけど、たまーにヤフオクなんかで出てくると、ビックリするような値段になっており、いつも断念。
その意味でこの音盤は、途中のスピーチなんかはカットされているけど、曲が聴けるだけでもありがたい。
もちろん海賊盤の是非、という意見はあるのだけど、それはこの際置いておいて。
どの曲も、会場に満ちた「くだけた空気」そのものが伝わってくるかのような演奏。
かといってもちろん手抜きなのではなく、むしろ「そういう空気感」だからこそ、レニーの溌剌さが直接響いてくる、といった方が適切。
例えばロッシーニ、最後の加速とラストに被さる拍手。
普通なら「フライング拍手!」なんて悪し様に言われるだろうけど、「逆にそれがいいやん」て感じ。
キャンディード、どちらかと言えば、軽く流しているのだけれど、居並ぶベタな名曲たちに比してまったく負けないその存在感に感動する。(身びいき??
マイスタージンガーは、あっけらかんとした開けっぴろげな歌わせ方。
質実な感じではなく、滔々とした広い流れというよりサクサクした歩みが印象的。
大学祝典序曲では、NYP盤のような最後の“ど”タメ(笑)はなし。
またまた終結前から拍手しちゃうお客にこちらももう笑うしかない。
唯一残念なのは、途中のスピーチが半分も理解できないこと。
お客もめっちゃ笑ってるのに。
ああ、もっと英語が分かればなぁ。(苦笑
フィルアップのマーラー。
DG盤やSONY盤よりもちょっぴり後年の録音。
この曲聴くのもずいぶん久しぶり。
ていうか、レニー盤しか持っていないのだが。(汗
身をよじるほどに美しく、それでいて痛切な叫びに満ちている。
発狂寸前のところで踏みとどまる、その残酷なまでの美しさ。
やっぱ全曲盤も後学のために聴かねばダメかな。
CD-Rの青盤。
最後の1曲以外は、本来ボストン・ポップスの自主製作盤で出ているもの。
現物が欲しいのだけど、たまーにヤフオクなんかで出てくると、ビックリするような値段になっており、いつも断念。
その意味でこの音盤は、途中のスピーチなんかはカットされているけど、曲が聴けるだけでもありがたい。
もちろん海賊盤の是非、という意見はあるのだけど、それはこの際置いておいて。
どの曲も、会場に満ちた「くだけた空気」そのものが伝わってくるかのような演奏。
かといってもちろん手抜きなのではなく、むしろ「そういう空気感」だからこそ、レニーの溌剌さが直接響いてくる、といった方が適切。
例えばロッシーニ、最後の加速とラストに被さる拍手。
普通なら「フライング拍手!」なんて悪し様に言われるだろうけど、「逆にそれがいいやん」て感じ。
キャンディード、どちらかと言えば、軽く流しているのだけれど、居並ぶベタな名曲たちに比してまったく負けないその存在感に感動する。(身びいき??
マイスタージンガーは、あっけらかんとした開けっぴろげな歌わせ方。
質実な感じではなく、滔々とした広い流れというよりサクサクした歩みが印象的。
大学祝典序曲では、NYP盤のような最後の“ど”タメ(笑)はなし。
またまた終結前から拍手しちゃうお客にこちらももう笑うしかない。
唯一残念なのは、途中のスピーチが半分も理解できないこと。
お客もめっちゃ笑ってるのに。
ああ、もっと英語が分かればなぁ。(苦笑
フィルアップのマーラー。
DG盤やSONY盤よりもちょっぴり後年の録音。
この曲聴くのもずいぶん久しぶり。
ていうか、レニー盤しか持っていないのだが。(汗
身をよじるほどに美しく、それでいて痛切な叫びに満ちている。
発狂寸前のところで踏みとどまる、その残酷なまでの美しさ。
やっぱ全曲盤も後学のために聴かねばダメかな。
通勤ミュージック~090627 ― 2009/06/27 18:00:28
*グールド・コンダクツ&プレイズ・ワーグナー
1. ジークフリート牧歌(オリジナル版/トロント響のメンバー)
2.「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲(グールド編)
3.「神々のたそがれ」~夜明けとジークフリートのラインへの旅(同)
4.ジークフリート牧歌(同)
グールドの指揮とピアノによるワグナー。
最晩年に「これからは指揮者になる」て言ってたグールド。
結局この1曲目のジークフリート牧歌が最後の録音になっちゃったわけだけど、もしもう少し長生きしていたら、何の曲を指揮して(そして録音して)いたんだろうか。
そのジークフリート牧歌。
オリジナルの編成がインティメートな感じを強調する。
テンポはかなりゆっくりめ。
でもべたつくのではなく、むしろカラリとした感じ。
各楽器やライトモティーフの明晰な浮かび上がり方に、さすがの知性が垣間見える。
ピアノ演奏で見せる「驚き」よりも、むしろ温かな感じが伝わってくるのが面白い。
意図をオケに伝えきれていないのか、どことなくギクシャクするところもあるけれど、それさえほのかな人間味に感じてしまう。
残り3曲はさすが?のグールド節。
まずはマイスタージンガー。
ずっしりと重心低く始めておきながら、自然と軽さや愉しさへと移行するそのマジック。
中間部のカノン風のところで出るお約束の「うた」!(笑
対位法的な掛け合いで見せる透明さ。
むしろオケでは埋没している響きが見事に「見えて」いる。
ジークフリートのラインへの旅。
何度か書いていると思うけど、この曲はホント好き。
クナやマタチッチで熱く語ったような神々の響き、というものとはもちろん異質だけど、ある意味「同じ音色」であるピアノだからこそ、ジークフリートとブリュンヒルデの呼びかわしがくっきりと際立つ。
そして何より、ライン川を渡るときのあのライトモティーフの粒立ち!
まさに言葉通りキラキラと、ラインの妖精の歌声が見えてくる。
オケによる「音の饗宴」でないからこそ、その(ある意味)ハッタリに騙されないでこの曲を味わえる。
ピアノで演奏してもこんなに魅力的なんて!
締めのジークフリート牧歌、アゲイン。(笑
もちろん1曲目より前に録音されているわけだけど、ここでグールドがしたこと、そして「ピアノでは」できないと感じたこと、って何だろうと考えて聴くと、1曲目がまた違って聞こえてくるから不思議。
1. ジークフリート牧歌(オリジナル版/トロント響のメンバー)
2.「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲(グールド編)
3.「神々のたそがれ」~夜明けとジークフリートのラインへの旅(同)
4.ジークフリート牧歌(同)
グールドの指揮とピアノによるワグナー。
最晩年に「これからは指揮者になる」て言ってたグールド。
結局この1曲目のジークフリート牧歌が最後の録音になっちゃったわけだけど、もしもう少し長生きしていたら、何の曲を指揮して(そして録音して)いたんだろうか。
そのジークフリート牧歌。
オリジナルの編成がインティメートな感じを強調する。
テンポはかなりゆっくりめ。
でもべたつくのではなく、むしろカラリとした感じ。
各楽器やライトモティーフの明晰な浮かび上がり方に、さすがの知性が垣間見える。
ピアノ演奏で見せる「驚き」よりも、むしろ温かな感じが伝わってくるのが面白い。
意図をオケに伝えきれていないのか、どことなくギクシャクするところもあるけれど、それさえほのかな人間味に感じてしまう。
残り3曲はさすが?のグールド節。
まずはマイスタージンガー。
ずっしりと重心低く始めておきながら、自然と軽さや愉しさへと移行するそのマジック。
中間部のカノン風のところで出るお約束の「うた」!(笑
対位法的な掛け合いで見せる透明さ。
むしろオケでは埋没している響きが見事に「見えて」いる。
ジークフリートのラインへの旅。
何度か書いていると思うけど、この曲はホント好き。
クナやマタチッチで熱く語ったような神々の響き、というものとはもちろん異質だけど、ある意味「同じ音色」であるピアノだからこそ、ジークフリートとブリュンヒルデの呼びかわしがくっきりと際立つ。
そして何より、ライン川を渡るときのあのライトモティーフの粒立ち!
まさに言葉通りキラキラと、ラインの妖精の歌声が見えてくる。
オケによる「音の饗宴」でないからこそ、その(ある意味)ハッタリに騙されないでこの曲を味わえる。
ピアノで演奏してもこんなに魅力的なんて!
締めのジークフリート牧歌、アゲイン。(笑
もちろん1曲目より前に録音されているわけだけど、ここでグールドがしたこと、そして「ピアノでは」できないと感じたこと、って何だろうと考えて聴くと、1曲目がまた違って聞こえてくるから不思議。


最近のコメント