ミチョランマ踏破は一歩ずつ/ピアソラ、CM音楽、ジュリーニ。 ― 2019/10/15 00:30:31
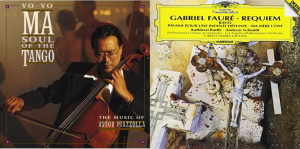
土曜日の台風で外仕事が飛び、図らずもその日から3連休になった。
シフト勤務なので、2連休はたまにあっても3連休以上なんて夏休みか冬休みくらいしかない。
不幸中の幸い、という言い方が適切かどうかは分からないけど、(特に土曜は)外に出るわけにも行かないので家で作業が色々と捗った。
日曜の夜。
ミチョランマの山に埋もれていた、「ヨーヨー・マ・プレイズ・ピアソラ」を聴いた。
買ったことすら忘れていた(苦笑)。
ピアソラはリベルタンゴしか知らない無知な身だが、どれも聴きやすかった。
「フガータ」と「タンゴ組曲」のアレグロが気に入った。
しかしこのアルバム、もう20年以上前になるのか……。
サントリーローヤルのCMで見たの(聴いたの?)、数年前とは言わないまでも、10年くらい前のような気がしてた。
時の経つ速さに震える。
CMと言えば、
・アロンアルファ:割れたレコードを再現するやつで流れるチェロの独奏曲
・ハーゲンダッツ:土俗的なバレエ音楽風の曲
がずっと何なのか分からなくてモヤモヤしたまま人生を送ってる。
後者はCMオリジナルの可能性も高いけど、前者は多分クラシックなんだよな……。
今ならググればすぐ分かるんだけど、なにせ時代が時代。
どちらも20年以上前。
ちなみに25年以上前の「ビートたけしのつくり方」というバラエティの1コーナーに「大家族主義」というミニドラマがあって、そのテーマ曲がモーツァルト風の軽快な楽曲だったけど、観ている当時は知らない曲だった。
それがその数年後に買ったCDに偶然入ってた。
フォーレの歌劇「ペネロープ」前奏曲だった。
全然モーツァルトじゃあない(苦笑)。
そんな偶然もあるので、上のふたつにもいつか出会えるのではと期待している。
翌月曜は連休の締めに、ジュリーニが指揮するフォーレのレクイエム、ラヴェルのマ・メール・ロワを聴いた。
前者のサンクトゥスにあふれる歌心。
後者の緻密でありながらせせこましくなく、むしろゆとりをもって聞こえてくる音像。
特に終曲「妖精の園」の余裕に満ちた締めくくり。
そういったジュリーニの歌心や緻密さの魅力に気づたのは、オッサンになってからだなぁ……。
若いときはもっと「渋い」だけの人と思ってたきらいがある。
ちなみにジュリーニ、VPOボックスとソニーボックスを買ってるのに(当然?)ミチョランマ。
これもいつかは手を付けないとね……。
ただ、何となくこの2日で「聴きぐせ」ついてきてるの良い気がする。
少しずつでも。
とにかく色んなやり方で、まずはミチョランマを減らしていきたいものです。
まだブラ2しかしてない、ムラヴィンスキーのボックス企画もちゃんとやりますよ?(笑)。
多分次はワグナー聴き比べ。
まあ、ぼちぼちと。
シフト勤務なので、2連休はたまにあっても3連休以上なんて夏休みか冬休みくらいしかない。
不幸中の幸い、という言い方が適切かどうかは分からないけど、(特に土曜は)外に出るわけにも行かないので家で作業が色々と捗った。
日曜の夜。
ミチョランマの山に埋もれていた、「ヨーヨー・マ・プレイズ・ピアソラ」を聴いた。
買ったことすら忘れていた(苦笑)。
ピアソラはリベルタンゴしか知らない無知な身だが、どれも聴きやすかった。
「フガータ」と「タンゴ組曲」のアレグロが気に入った。
しかしこのアルバム、もう20年以上前になるのか……。
サントリーローヤルのCMで見たの(聴いたの?)、数年前とは言わないまでも、10年くらい前のような気がしてた。
時の経つ速さに震える。
CMと言えば、
・アロンアルファ:割れたレコードを再現するやつで流れるチェロの独奏曲
・ハーゲンダッツ:土俗的なバレエ音楽風の曲
がずっと何なのか分からなくてモヤモヤしたまま人生を送ってる。
後者はCMオリジナルの可能性も高いけど、前者は多分クラシックなんだよな……。
今ならググればすぐ分かるんだけど、なにせ時代が時代。
どちらも20年以上前。
ちなみに25年以上前の「ビートたけしのつくり方」というバラエティの1コーナーに「大家族主義」というミニドラマがあって、そのテーマ曲がモーツァルト風の軽快な楽曲だったけど、観ている当時は知らない曲だった。
それがその数年後に買ったCDに偶然入ってた。
フォーレの歌劇「ペネロープ」前奏曲だった。
全然モーツァルトじゃあない(苦笑)。
そんな偶然もあるので、上のふたつにもいつか出会えるのではと期待している。
翌月曜は連休の締めに、ジュリーニが指揮するフォーレのレクイエム、ラヴェルのマ・メール・ロワを聴いた。
前者のサンクトゥスにあふれる歌心。
後者の緻密でありながらせせこましくなく、むしろゆとりをもって聞こえてくる音像。
特に終曲「妖精の園」の余裕に満ちた締めくくり。
そういったジュリーニの歌心や緻密さの魅力に気づたのは、オッサンになってからだなぁ……。
若いときはもっと「渋い」だけの人と思ってたきらいがある。
ちなみにジュリーニ、VPOボックスとソニーボックスを買ってるのに(当然?)ミチョランマ。
これもいつかは手を付けないとね……。
ただ、何となくこの2日で「聴きぐせ」ついてきてるの良い気がする。
少しずつでも。
とにかく色んなやり方で、まずはミチョランマを減らしていきたいものです。
まだブラ2しかしてない、ムラヴィンスキーのボックス企画もちゃんとやりますよ?(笑)。
多分次はワグナー聴き比べ。
まあ、ぼちぼちと。
アリス=紗良・オット@初台オペラシティ ― 2018/11/27 01:01:58
2カ月近く前ですが……ブログ書き癖(?)つけるためにも、と思い書く。
9月27日、初台オペラシティ。
随分久しぶり(多分前のソロツアー以来?)に、アリス=紗良・オットのコンサート。
大好きなピアニストと言いつつ、2年ぶりかぁ。
新譜「ナイトフォール」発売に伴うこともあり、フレンチ中心のプログラム。
リストやショパンに定評のある彼女なので、フレンチはどうかな?と思いつつやったけど、結果的には最高やった。
前半はベルガマスク組曲、ショパンのノクターン(1・2・13番)とバラード1番。
休憩挟んだ後半はドビュッシーの「夢想」、サティ小品(グノシエンヌ1、ジムノペディ1、グノシエンヌ3)と夜のガスパール……という3つのくくりで構成されていた。
いつも以上にほの暗いライティング含め、まさに夢想が次々展開していく感じ。
しかし毎度安定のスロースターター(苦笑)。
ベルガマスク組曲は少々硬さあるというか、透明感欠けるかなぁ、なんて思ったり。
一番好きな「パスピエ」こそ躍動感あったけど。
まぁこの曲はどうしてもフランソワの名演と比べてしまうからな……(クラヲタめんどくさいあるあるw)。
ショパンのターンはさすがのファンタジー炸裂。
ノクターン2番の、弾き崩しギリギリで踏みとどまるアゴーギク、バラード終盤の追い込み。
この固まりをひとつの「物語」として提示しているのが、曲間を殆ど開けずに進めたことからも伝わってきた。
聴いてるこっちも集中してヘトヘトw
てかバラードCD早く出してよ(笑)。
休憩後のターンは更に素晴らしかった。サティの艶っぽさ、蠱惑感(それが必要なのかという声はさておき)。
その陶酔から醒めさせず、ショパンの時と同じくほぼ「ひと続き」で始まるラヴェル。
夜のガスパールと言えばアルゲリッチの名盤が個人的には好きやけど、遜色ないし……何よりやっぱ生は良い!
3曲の描き分け、そしてスカルボの熱演。客席も息をのむのが伝わってきた。
そして彼女が弾き終えたあと、フラブラも拍手もなく、しばし余韻を皆で共有してから大喝采。あれはグッときたなぁ。
……女性に「ブラボー」って言うのは何だかなぁとは思うけど(クラヲタめんどくさいその2。苦笑)
ツアーラストってことや、お父様のアレもあったのかな? 終演後感極まってた彼女の姿にこちらも涙。
アンコールは予想通り(アルバム曲で唯一プログラムに乗ってなかったから)、亡き王女のためのパヴァーヌ。
フレンチお得意な先達とは少し違えど、煌めきの中に名残惜しさが見えるような?「残心」的な引き取り方が印象的。
余談。
サイン会無くて残念w そのまま帰国(と書くのが彼女の場合適切か悩む……)したからかな。
あと今回今までになくチケ取るの苦労して、嬉しい驚きの半面、次回から気をつけねばと思った次第。
数年前から拝聴拝見してるけど、プレイガイド完売、当券無しとか初やったんちゃうかなぁ。
備忘録。
過去のアリスコンサート行った記録。
やっぱり今回過去最大間隔空いてるね。
年一は行かねば。
20180927 初台オペラシティ
20160930 初台オペラシティ
20150519 初台オペラシティ
20140624 すみだトリフォニーホール(トリスターノとのデュオ)
20140610 杉並公会堂
20140312 池袋芸術劇場(グリーグ・コンチェルト)
20120608 東京文化会館 (リスト・コンチェルト)
20110112 初台オペラシティ
20110106 サントリーホール(リスト・コンチェルト)
20100919 池袋芸術劇場(チャイコ・コンチェルト)
9月27日、初台オペラシティ。
随分久しぶり(多分前のソロツアー以来?)に、アリス=紗良・オットのコンサート。
大好きなピアニストと言いつつ、2年ぶりかぁ。
新譜「ナイトフォール」発売に伴うこともあり、フレンチ中心のプログラム。
リストやショパンに定評のある彼女なので、フレンチはどうかな?と思いつつやったけど、結果的には最高やった。
前半はベルガマスク組曲、ショパンのノクターン(1・2・13番)とバラード1番。
休憩挟んだ後半はドビュッシーの「夢想」、サティ小品(グノシエンヌ1、ジムノペディ1、グノシエンヌ3)と夜のガスパール……という3つのくくりで構成されていた。
いつも以上にほの暗いライティング含め、まさに夢想が次々展開していく感じ。
しかし毎度安定のスロースターター(苦笑)。
ベルガマスク組曲は少々硬さあるというか、透明感欠けるかなぁ、なんて思ったり。
一番好きな「パスピエ」こそ躍動感あったけど。
まぁこの曲はどうしてもフランソワの名演と比べてしまうからな……(クラヲタめんどくさいあるあるw)。
ショパンのターンはさすがのファンタジー炸裂。
ノクターン2番の、弾き崩しギリギリで踏みとどまるアゴーギク、バラード終盤の追い込み。
この固まりをひとつの「物語」として提示しているのが、曲間を殆ど開けずに進めたことからも伝わってきた。
聴いてるこっちも集中してヘトヘトw
てかバラードCD早く出してよ(笑)。
休憩後のターンは更に素晴らしかった。サティの艶っぽさ、蠱惑感(それが必要なのかという声はさておき)。
その陶酔から醒めさせず、ショパンの時と同じくほぼ「ひと続き」で始まるラヴェル。
夜のガスパールと言えばアルゲリッチの名盤が個人的には好きやけど、遜色ないし……何よりやっぱ生は良い!
3曲の描き分け、そしてスカルボの熱演。客席も息をのむのが伝わってきた。
そして彼女が弾き終えたあと、フラブラも拍手もなく、しばし余韻を皆で共有してから大喝采。あれはグッときたなぁ。
……女性に「ブラボー」って言うのは何だかなぁとは思うけど(クラヲタめんどくさいその2。苦笑)
ツアーラストってことや、お父様のアレもあったのかな? 終演後感極まってた彼女の姿にこちらも涙。
アンコールは予想通り(アルバム曲で唯一プログラムに乗ってなかったから)、亡き王女のためのパヴァーヌ。
フレンチお得意な先達とは少し違えど、煌めきの中に名残惜しさが見えるような?「残心」的な引き取り方が印象的。
余談。
サイン会無くて残念w そのまま帰国(と書くのが彼女の場合適切か悩む……)したからかな。
あと今回今までになくチケ取るの苦労して、嬉しい驚きの半面、次回から気をつけねばと思った次第。
数年前から拝聴拝見してるけど、プレイガイド完売、当券無しとか初やったんちゃうかなぁ。
備忘録。
過去のアリスコンサート行った記録。
やっぱり今回過去最大間隔空いてるね。
年一は行かねば。
20180927 初台オペラシティ
20160930 初台オペラシティ
20150519 初台オペラシティ
20140624 すみだトリフォニーホール(トリスターノとのデュオ)
20140610 杉並公会堂
20140312 池袋芸術劇場(グリーグ・コンチェルト)
20120608 東京文化会館 (リスト・コンチェルト)
20110112 初台オペラシティ
20110106 サントリーホール(リスト・コンチェルト)
20100919 池袋芸術劇場(チャイコ・コンチェルト)
通勤ミュージック~090620 ― 2009/06/24 01:29:52

*ブラームス&シベリウス:ヴァイオリン協奏曲(ヌヴー、ドヴロウェン&ジュスキント/PO)、ラヴェル: ハバネラ形式の小品、スカラテスク:バガテル(ヌヴー、ジャン・ヌヴー)
言わずと知れた名盤……だけど初聴。
と言うか、ヌヴー自体が初聴。(汗
聴いたのはオーパス蔵。
個人的に、ヴァイオリニストは女性に好きな人が多い。
ムターしかり、キョンファしかり。
……ずいぶん対照的なタイプだけど。(苦笑
ヌヴーの演奏は、情熱への耽溺と旋律への清冽さが、矛盾せずに共存している。
両曲とも、カデンツァやアインガング(指ならし)ではむせ返るような熱気をそのままぶつけてくる。
でも、オケと合わすところでは決して放埓にならない。
ある種の「枠」の中で、きちっと引き締まった「うた」が奏でられる。
ブラームスの2楽章がまさにその典型。
ぴんと背筋の張った歌い方で、すごく心がこもっている。
ただ、3楽章はもう少し熱気のほうが前面に出ても……という感じがした。
イッセルシュテットとのライヴ盤(これまた有名)は、もっと「熱い」と言う人が多いので、いずれそちらも聴かなきゃ。
この音盤単体で言えば、シベリウスの方が名演かも。
何と言っても、先述した「熱気と知性の共存」がより高度に結晶化している。
この曲は、ボク的には「マイ初演」であるキョンファの録音を超えるものはいまだないのだけれど、それとは違う方向性、ということで評価大。
それこそキョンファだとほとんどケンカ腰というか、啖呵切るようにスリリングな3楽章も、腰を据えてじっくりと盛り上げていく。
一聴した時こそ、テンポ運びも含めて「大人しいかなぁ」なんて感じたのだけど、繰り返し聴くたびに、じわじわと熱を帯びながら終結へ向かう音楽作りの説得力にやられた。
フィルアップの2曲はコンチェルトとは違うヌヴーの一面が垣間見える感じ。
艶っぽいというか、色っぽいと言うか。
曲想に合わせてのことだとは思うけど、その違いもまた興味深い。
もう少し長生きしてくれたら、ステレオで名盤を残してくれたんだろうな……。
チャイコンとか聴いてみたかったなー。
言わずと知れた名盤……だけど初聴。
と言うか、ヌヴー自体が初聴。(汗
聴いたのはオーパス蔵。
個人的に、ヴァイオリニストは女性に好きな人が多い。
ムターしかり、キョンファしかり。
……ずいぶん対照的なタイプだけど。(苦笑
ヌヴーの演奏は、情熱への耽溺と旋律への清冽さが、矛盾せずに共存している。
両曲とも、カデンツァやアインガング(指ならし)ではむせ返るような熱気をそのままぶつけてくる。
でも、オケと合わすところでは決して放埓にならない。
ある種の「枠」の中で、きちっと引き締まった「うた」が奏でられる。
ブラームスの2楽章がまさにその典型。
ぴんと背筋の張った歌い方で、すごく心がこもっている。
ただ、3楽章はもう少し熱気のほうが前面に出ても……という感じがした。
イッセルシュテットとのライヴ盤(これまた有名)は、もっと「熱い」と言う人が多いので、いずれそちらも聴かなきゃ。
この音盤単体で言えば、シベリウスの方が名演かも。
何と言っても、先述した「熱気と知性の共存」がより高度に結晶化している。
この曲は、ボク的には「マイ初演」であるキョンファの録音を超えるものはいまだないのだけれど、それとは違う方向性、ということで評価大。
それこそキョンファだとほとんどケンカ腰というか、啖呵切るようにスリリングな3楽章も、腰を据えてじっくりと盛り上げていく。
一聴した時こそ、テンポ運びも含めて「大人しいかなぁ」なんて感じたのだけど、繰り返し聴くたびに、じわじわと熱を帯びながら終結へ向かう音楽作りの説得力にやられた。
フィルアップの2曲はコンチェルトとは違うヌヴーの一面が垣間見える感じ。
艶っぽいというか、色っぽいと言うか。
曲想に合わせてのことだとは思うけど、その違いもまた興味深い。
もう少し長生きしてくれたら、ステレオで名盤を残してくれたんだろうな……。
チャイコンとか聴いてみたかったなー。
通勤ミュージック~090415 ― 2009/04/15 02:35:35

*ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」、B.チャイコフスキー:テーマと変奏曲(フェドセーエフ/モスクワ放送響)
このブログだったかな? mixiだったかな? 「展覧会の絵」(ラヴェル版)には、どうも個人的にしっくりくる演奏になかなか巡り会えてない、みたいなことを書いたのは。
まあそうは言っても、チャイ5みたいに「理想の一枚」を求めて山のように聴き漁っているわけではないので、自分の努力が足りない面もあるにはあるのだろうけれども。(苦笑
あくまでボクの中では、だけど、この曲には煌びやかな管弦楽効果よりも、もっと深い「うた」と言うか、“声のないレクイエム”のような演奏を期待しているところがある。
もちろん、ハルトマンの遺作展だけで作られたワケでもない、ていう昨今の説は知ってるのだけど。
その意味では、原曲のピアノ版の空気感を感じさせる演奏を探しているとも言える。
ただ、矛盾するようだけど、ラヴェルのアレンジはやっぱりすごいと思う。
冒頭のTp.にしろ、「古城」のSax.にしろ、ラヴェルが我々に刻印した「色」は、なかなか拭い難いものがどうしてもある。
それらを踏まえた上でこの音盤。
なかなか良かった。
100%、ではないけれど、かなり自分が「こうあってほしい(or こうしたい)」演奏スタイルに、今まで聴いた音盤では一番近かった。
まずは最初のプロムナード。
抑えた響きからもう期待大。
朗々、流々と吹かれるのはダメなので。
ほとんど間を置かずに始まる「こびと」。
暴力的でないがゆえに、所々で見せるドキッとするような打楽器の打ち込みがかえって怖い。
そして最後のまくり!
「古城」の墨色感。
この曲に関しては、もっとフランス風のアンニュイを前面に押し出したスタイルもありだと思うけど、個人的にはこの音盤のように思索や内省を感じさせる方が好きかな。
入念なテンポ操作の光る「チュルリー」。
特に中間部の遅めのユーモアには、「その手があるのか……」と感心しきり。
自然と加速して元に戻るのもうまい。
「ヴィドロ」も、プロムナード同様、抑制された音色が哀しみを誘う。
でもこの曲に関して言えば、もう少し「怒り」の表情付けもあってもいいかな?
「カタコンベ」の静謐な空気。
その中にピンと張った緊張感。
「バーバ・ヤガ」は、こけおどしでない腰の据わった響きに満足。
もっとTimp.が派手でもいいかもしれないけど、そういった効果を志向してないんだろうな。
そして「キエフ」の流れるような「うた」!
ここでバリバリブリブリ鳴らしまくるだけの演奏のいかに多いことか。
まさにその対極。
でももちろん小粒なのでは全くなく、骨太にずっしりと歌い込む。
最後のパウゼの後、ぐっと落としたテンポで振り返る。
長調なのに胸を締め付けられるような存在感。
まるでコラールのような佇まい。
ちょっと驚きなのは最後のド派手な鐘の連打。
うーん……これは要らなかったかなぁ?(苦笑
ちょっと雰囲気壊している気がする。
フィルアップのB.チャイコフスキーの曲は初聴き。
あまりロシア-ソ連の響きを感じさせない、不思議な曲。
このブログだったかな? mixiだったかな? 「展覧会の絵」(ラヴェル版)には、どうも個人的にしっくりくる演奏になかなか巡り会えてない、みたいなことを書いたのは。
まあそうは言っても、チャイ5みたいに「理想の一枚」を求めて山のように聴き漁っているわけではないので、自分の努力が足りない面もあるにはあるのだろうけれども。(苦笑
あくまでボクの中では、だけど、この曲には煌びやかな管弦楽効果よりも、もっと深い「うた」と言うか、“声のないレクイエム”のような演奏を期待しているところがある。
もちろん、ハルトマンの遺作展だけで作られたワケでもない、ていう昨今の説は知ってるのだけど。
その意味では、原曲のピアノ版の空気感を感じさせる演奏を探しているとも言える。
ただ、矛盾するようだけど、ラヴェルのアレンジはやっぱりすごいと思う。
冒頭のTp.にしろ、「古城」のSax.にしろ、ラヴェルが我々に刻印した「色」は、なかなか拭い難いものがどうしてもある。
それらを踏まえた上でこの音盤。
なかなか良かった。
100%、ではないけれど、かなり自分が「こうあってほしい(or こうしたい)」演奏スタイルに、今まで聴いた音盤では一番近かった。
まずは最初のプロムナード。
抑えた響きからもう期待大。
朗々、流々と吹かれるのはダメなので。
ほとんど間を置かずに始まる「こびと」。
暴力的でないがゆえに、所々で見せるドキッとするような打楽器の打ち込みがかえって怖い。
そして最後のまくり!
「古城」の墨色感。
この曲に関しては、もっとフランス風のアンニュイを前面に押し出したスタイルもありだと思うけど、個人的にはこの音盤のように思索や内省を感じさせる方が好きかな。
入念なテンポ操作の光る「チュルリー」。
特に中間部の遅めのユーモアには、「その手があるのか……」と感心しきり。
自然と加速して元に戻るのもうまい。
「ヴィドロ」も、プロムナード同様、抑制された音色が哀しみを誘う。
でもこの曲に関して言えば、もう少し「怒り」の表情付けもあってもいいかな?
「カタコンベ」の静謐な空気。
その中にピンと張った緊張感。
「バーバ・ヤガ」は、こけおどしでない腰の据わった響きに満足。
もっとTimp.が派手でもいいかもしれないけど、そういった効果を志向してないんだろうな。
そして「キエフ」の流れるような「うた」!
ここでバリバリブリブリ鳴らしまくるだけの演奏のいかに多いことか。
まさにその対極。
でももちろん小粒なのでは全くなく、骨太にずっしりと歌い込む。
最後のパウゼの後、ぐっと落としたテンポで振り返る。
長調なのに胸を締め付けられるような存在感。
まるでコラールのような佇まい。
ちょっと驚きなのは最後のド派手な鐘の連打。
うーん……これは要らなかったかなぁ?(苦笑
ちょっと雰囲気壊している気がする。
フィルアップのB.チャイコフスキーの曲は初聴き。
あまりロシア-ソ連の響きを感じさせない、不思議な曲。
通勤ミュージック~081219 ― 2008/12/19 18:30:52

*ベルリオーズ:幻想交響曲(クリュイタンス/パリ音楽院管弦楽団)
1964年5月10日東京文化会館での録音(Altus盤)。
POとのスタジオ盤とは違う熱演でつとに有名。
20年くらい前にはKING系のSevenSeasで出ていた。
高校時代に友人が持っていて、借りて聴いた記憶がある。
自分のモノとしてきちんと聴くのはそれ以来。(時がたつのは速いねぇ。
改めて聴くと、もちろん熱演であることは事実だけど、「我を忘れた」タイプではないことに気づく。
プログラム・ミュージックであるこの曲に対し、「1人称の解釈」でなく「3人称」として臨んでいるのが大きな特徴、だと感じた。
大事なのは「客体」ではなくて「3人称」なこと。
表題音楽性をのっけから無視して臨むのが「客体」なら(それはそれで貫徹しているならありだと思う。スキではないけど……苦笑)、「物語」の中に没入するのではなく、一歩引いて「語る」視点を持っているのが「3人称」なのかな、と。
そこばかり注目されがちな、4・5楽章の燃え上がりもそう。
もちろんラストのコーダなんて、Tb.が落ちるほどの加速だけれど、それは「語り口」に熱がこもったからであって、決して“髪振り乱して”という感じではない。
同じ「熱演」でもミュンシュ/パリ管との大きな違いはそこ。
……ちなみにミュンシュ盤は大好きですよ。(まあボクの趣味から想像付くでしょうけど。苦笑
それこそがクリュイタンスならではのニュアンス(エスプリ?)。
ちょっとドライな録音からも滲み出る、あまりに魅惑的な、「粋」なんだと思う。
その意味では、この曲の「痛さ」(=ストーカーさ。笑)は払拭されているとも言える。
(そう考えると、ホントの意味で一番コワイのはクレンペラー盤だな)
あと注目すべきは、クリュイタンスの音像づくりの立派さ。
カラリとしたオケの音を生かしつつ、例えば1楽章序奏最後のファゴット強調みたいに、思わぬところで耳を引かせる。
4・5楽章の低弦・Timp.のここ一番での強奏もその流れでとらえるべき。
そして忘れちゃいけないのがアンコールの2曲の完熟っぷり。
「古い城」の惻々たる寂しさ。
その中に潜む品のあるセクシーさ。
「ファランドール」の完全無欠のアッチェルランド。
むしろ押し出し強く堂々と始まるのに、気づけば魔法のように加速していく。
わずか3分半の奇跡、いや永遠の3分半の奇跡。
こんな演奏できるなら、寿命が1年くらい縮んだって構わない。
1964年5月10日東京文化会館での録音(Altus盤)。
POとのスタジオ盤とは違う熱演でつとに有名。
20年くらい前にはKING系のSevenSeasで出ていた。
高校時代に友人が持っていて、借りて聴いた記憶がある。
自分のモノとしてきちんと聴くのはそれ以来。(時がたつのは速いねぇ。
改めて聴くと、もちろん熱演であることは事実だけど、「我を忘れた」タイプではないことに気づく。
プログラム・ミュージックであるこの曲に対し、「1人称の解釈」でなく「3人称」として臨んでいるのが大きな特徴、だと感じた。
大事なのは「客体」ではなくて「3人称」なこと。
表題音楽性をのっけから無視して臨むのが「客体」なら(それはそれで貫徹しているならありだと思う。スキではないけど……苦笑)、「物語」の中に没入するのではなく、一歩引いて「語る」視点を持っているのが「3人称」なのかな、と。
そこばかり注目されがちな、4・5楽章の燃え上がりもそう。
もちろんラストのコーダなんて、Tb.が落ちるほどの加速だけれど、それは「語り口」に熱がこもったからであって、決して“髪振り乱して”という感じではない。
同じ「熱演」でもミュンシュ/パリ管との大きな違いはそこ。
……ちなみにミュンシュ盤は大好きですよ。(まあボクの趣味から想像付くでしょうけど。苦笑
それこそがクリュイタンスならではのニュアンス(エスプリ?)。
ちょっとドライな録音からも滲み出る、あまりに魅惑的な、「粋」なんだと思う。
その意味では、この曲の「痛さ」(=ストーカーさ。笑)は払拭されているとも言える。
(そう考えると、ホントの意味で一番コワイのはクレンペラー盤だな)
あと注目すべきは、クリュイタンスの音像づくりの立派さ。
カラリとしたオケの音を生かしつつ、例えば1楽章序奏最後のファゴット強調みたいに、思わぬところで耳を引かせる。
4・5楽章の低弦・Timp.のここ一番での強奏もその流れでとらえるべき。
そして忘れちゃいけないのがアンコールの2曲の完熟っぷり。
「古い城」の惻々たる寂しさ。
その中に潜む品のあるセクシーさ。
「ファランドール」の完全無欠のアッチェルランド。
むしろ押し出し強く堂々と始まるのに、気づけば魔法のように加速していく。
わずか3分半の奇跡、いや永遠の3分半の奇跡。
こんな演奏できるなら、寿命が1年くらい縮んだって構わない。

最近のコメント