通勤ミュージック~090430 ― 2009/05/01 02:50:11
*シューマン:交響曲第2番・3番(エッシェンバッハ/NDR)
前々々回の続き。(笑
2番も1・4番とコンセプトは同じ。
すっきりしていて、輪郭がくっきり見える演奏。
Timp.や金管が随所で強奏されるのだけど、威圧的でなく常に透き通っている。
1・2楽章にほとんど間を置かず続けているのが面白い。
(単一形式のはずの)4番で空けていたのに。(苦笑
2楽章の最後、ショルティやレニーのように加速しているけれど、それもどこか鼻歌のように穏やか。
3楽章も決して詠嘆的に沈み込むことなく、しずしずと進んでいく。
4楽章も「暗→明」の勝利感よりも、全体を貫くなだらかさが不思議。
最後に加速してくのがユニークだけど、それも決して汗ばんだものにはならない。
何というか、妙な浮遊感に包まれた2番。
だったらショルティのような力業や、クーベリックの木訥さや、サヴァリッシュの自然さの方がいいのかも、と正直思わなくもないが、「脱・精神病的シューマン」のひとつの解釈としてありなのだろう。
「ライン」はこの全集で一番いいかも。
とにかくスコーンと突き抜けていて、鳴りまくる1楽章。
屈託のないホルンの響きが、曲想と絶妙にマッチしている。
子細構わずグイグイ進む2楽章も爽快。
一番すごいのが快速の終楽章。
ちょっぴりアンサンブルが乱れるのだけど、そんなの気にしない。
それもまた良し。(笑
こう考えると、「ライン」てシューマンの交響曲の中では異質なのかな、て思う。
「シューマンらしくない」ものを受け入れる幅がもともとある、と言う点で。
前々々回の続き。(笑
2番も1・4番とコンセプトは同じ。
すっきりしていて、輪郭がくっきり見える演奏。
Timp.や金管が随所で強奏されるのだけど、威圧的でなく常に透き通っている。
1・2楽章にほとんど間を置かず続けているのが面白い。
(単一形式のはずの)4番で空けていたのに。(苦笑
2楽章の最後、ショルティやレニーのように加速しているけれど、それもどこか鼻歌のように穏やか。
3楽章も決して詠嘆的に沈み込むことなく、しずしずと進んでいく。
4楽章も「暗→明」の勝利感よりも、全体を貫くなだらかさが不思議。
最後に加速してくのがユニークだけど、それも決して汗ばんだものにはならない。
何というか、妙な浮遊感に包まれた2番。
だったらショルティのような力業や、クーベリックの木訥さや、サヴァリッシュの自然さの方がいいのかも、と正直思わなくもないが、「脱・精神病的シューマン」のひとつの解釈としてありなのだろう。
「ライン」はこの全集で一番いいかも。
とにかくスコーンと突き抜けていて、鳴りまくる1楽章。
屈託のないホルンの響きが、曲想と絶妙にマッチしている。
子細構わずグイグイ進む2楽章も爽快。
一番すごいのが快速の終楽章。
ちょっぴりアンサンブルが乱れるのだけど、そんなの気にしない。
それもまた良し。(笑
こう考えると、「ライン」てシューマンの交響曲の中では異質なのかな、て思う。
「シューマンらしくない」ものを受け入れる幅がもともとある、と言う点で。
通勤ミュージック~090503 ― 2009/05/03 23:44:02
*シベリウス:交響曲第1番、「カレリア」組曲(カラヤン/BPO)
カラヤンのシベリウス演奏は、作曲者自身が評価していたとのことだけど、いわゆる「寒色・北欧系」(?)の解釈とは一線を画しているのは明らか。
交響曲全集をとりあえず(苦笑)作るのがお得意のカラヤンだけど、なぜか3番の録音がないのが謎。
個人的には、カラヤンのシベリウスって嫌いではない。
後半の「難解」な曲(4~7番)の「マイ初演」がDGの録音で、特に4番や6番といった謎めいた曲を、ひんやりとした手触りをそのままの形で音にしたような彼の音盤で初体験できたことが「食わず嫌い」にならずに済んだ理由だ、と感謝しているから。
4~7番はEMIでもBPOと録音しているらしいので、いつかは聴いてもいいかな。
メジャーどころではやはり2番、ということになるのだろうけど、これはPO・BPOの音盤共に所有。
若々しい覇気のある前者、大柄な中、カラヤン美学に満ちあふれた後者とも、それなりに面白い。
翻って当音盤。
両曲とも唯一の録音らしい。
その意味ではカラヤンの中で「落ち穂拾い」的意図があったのだろうか?
なぜそんな事を思ったかというと、正直に言ってしまえば、シベリウスの音盤としても、「カラヤンのシベリウス」としても若干物足りないので。
まずは交響曲。
1楽章の劇性は期待通りで、Vn.やFl.のソロにもひっそりとした佇まいよりクールな目線が配されているのが「いかにも」なんだけど、それが全体を通してやり切っている感じにならない。
主部なんて、もっとドラマティックにやっていいのではないか。
2楽章も何だかよく分からないうちにフニャフニャ終わってしまう。
スケルツォも当然土俗性は一切なし。
かといって、BPOの威力を発揮するでもなく、淡々としている。
大泣きしない、フィナーレ冒頭の沈み込んだ感じはハッとさせられる。
ここは悪くない。
しかし、主部に入ると、意外にあっさり。
もっと曲とオケを自在にドライヴする感じなのかと思っていただけに拍子抜け。
コーダの壮大な幕切れは、ピッチカートに重い余韻があっていいけれど、何だかそれまでの表情とは解離しているようにも感じる。
うーん。
うまく言えないけど、「もっとカラヤンらしくてもいいのに!」と(珍しく)歯がゆく感じる音盤、とでも書けば伝わるだろうか。
「カレリア組曲」、この曲大好きなのだけど、これまた肩すかし。
もちろんカラヤンだから、鄙びた感じがないのは承知の上だけど、それにしてもアクが無さ過ぎる。
なだらかにしようと意識しすぎなのだろうか?
もちろん所々でキラキラとしたゴージャスさがかいま見えるのだけど、それがやや腰の重さにつながっている気もするし……。
それならそれで、ドイツの舞曲のように渋い肌触りに仕上げることも出来ただろうに、そこまでのごつさはない。
両曲ともに、残念ながらちょっと消化不良な感じ……。
ただ、これってもしかしたら音盤(ソフト)自体に問題があるのかもしれない。
何だか妙にダイナミックレンジが広すぎる録音で、交響曲の1楽章(弦の刻み)やカレリアの冒頭なんて、相当音を大きくしないと聞こえないほどやせた感じ。
かといって音量を大きくしたままだと、fのところでもの凄い圧迫感。
入手したのは国内盤の中古なんだけど。別盤で聴き直すと、印象変わるかも?
カラヤンのシベリウス演奏は、作曲者自身が評価していたとのことだけど、いわゆる「寒色・北欧系」(?)の解釈とは一線を画しているのは明らか。
交響曲全集をとりあえず(苦笑)作るのがお得意のカラヤンだけど、なぜか3番の録音がないのが謎。
個人的には、カラヤンのシベリウスって嫌いではない。
後半の「難解」な曲(4~7番)の「マイ初演」がDGの録音で、特に4番や6番といった謎めいた曲を、ひんやりとした手触りをそのままの形で音にしたような彼の音盤で初体験できたことが「食わず嫌い」にならずに済んだ理由だ、と感謝しているから。
4~7番はEMIでもBPOと録音しているらしいので、いつかは聴いてもいいかな。
メジャーどころではやはり2番、ということになるのだろうけど、これはPO・BPOの音盤共に所有。
若々しい覇気のある前者、大柄な中、カラヤン美学に満ちあふれた後者とも、それなりに面白い。
翻って当音盤。
両曲とも唯一の録音らしい。
その意味ではカラヤンの中で「落ち穂拾い」的意図があったのだろうか?
なぜそんな事を思ったかというと、正直に言ってしまえば、シベリウスの音盤としても、「カラヤンのシベリウス」としても若干物足りないので。
まずは交響曲。
1楽章の劇性は期待通りで、Vn.やFl.のソロにもひっそりとした佇まいよりクールな目線が配されているのが「いかにも」なんだけど、それが全体を通してやり切っている感じにならない。
主部なんて、もっとドラマティックにやっていいのではないか。
2楽章も何だかよく分からないうちにフニャフニャ終わってしまう。
スケルツォも当然土俗性は一切なし。
かといって、BPOの威力を発揮するでもなく、淡々としている。
大泣きしない、フィナーレ冒頭の沈み込んだ感じはハッとさせられる。
ここは悪くない。
しかし、主部に入ると、意外にあっさり。
もっと曲とオケを自在にドライヴする感じなのかと思っていただけに拍子抜け。
コーダの壮大な幕切れは、ピッチカートに重い余韻があっていいけれど、何だかそれまでの表情とは解離しているようにも感じる。
うーん。
うまく言えないけど、「もっとカラヤンらしくてもいいのに!」と(珍しく)歯がゆく感じる音盤、とでも書けば伝わるだろうか。
「カレリア組曲」、この曲大好きなのだけど、これまた肩すかし。
もちろんカラヤンだから、鄙びた感じがないのは承知の上だけど、それにしてもアクが無さ過ぎる。
なだらかにしようと意識しすぎなのだろうか?
もちろん所々でキラキラとしたゴージャスさがかいま見えるのだけど、それがやや腰の重さにつながっている気もするし……。
それならそれで、ドイツの舞曲のように渋い肌触りに仕上げることも出来ただろうに、そこまでのごつさはない。
両曲ともに、残念ながらちょっと消化不良な感じ……。
ただ、これってもしかしたら音盤(ソフト)自体に問題があるのかもしれない。
何だか妙にダイナミックレンジが広すぎる録音で、交響曲の1楽章(弦の刻み)やカレリアの冒頭なんて、相当音を大きくしないと聞こえないほどやせた感じ。
かといって音量を大きくしたままだと、fのところでもの凄い圧迫感。
入手したのは国内盤の中古なんだけど。別盤で聴き直すと、印象変わるかも?
通勤ミュージック~090510 ― 2009/05/10 23:52:24
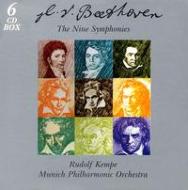
*ベートーヴェン:交響曲第1番・第5番(ケンペ/ミュンヘンpo)
久々復活、「もっとベートーヴェン交響曲全集」(爆)。
とりあえず昨年末に「第9三昧」で聴いた盤は完結させねば、てことでケンペ(次はコンヴィチュニーの予定)。
まずは1番。
1楽章の冒頭の1音から澄み渡った空気が支配。
特別なことをするのではなく、ただ誠実に音を紡いでいく。
青春の息吹きや若々しさが「現在進行形」として表出されるのではなく、老成した大人がじっくりと回顧するような感じ……と言えばいいだろうか。
例えば終楽章の主部への入りで丁寧に弾き込まれる弦。
若さや熱気を過剰に強調することなく、落ち着いた身振りなのが清々しい。
ベートーヴェンに限らず、他の作曲家の曲でもそうなのだけど、ケンペは出自(オーボエ奏者)ゆえか、常に木管が美しい。
この曲でも明るくサウンドする管楽器が印象的。
そして5番。
1楽章では乾いた響きの、ザクザクした肌触りに驚かされる。
運命動機の2回目のフェルマータを気持ちデクレッシェンドさせる技。
その中で引き立つオーボエのソロのたおやかさ(ここでも木管だ!)。
運命動機の2回目の後に、「慣例」のパウゼを置かないことによる切迫感。
2楽章、背後の低弦や管楽器の刻みがしっかりと弾き(吹き)こまれているのに感心。
とにかく清潔な佇まいに、聴いているこちらもシャンとする。
結尾のゆったりとした納め方がロマンティック……だけど漂う「懐かしさ」。
スケルツォはじっくりと進め、決して煽らない。
この楽章に内在する「ユーモア」を敢えて強調しない。
ひたすらまじめに向き合う。
当然、3~4楽章間のブリッジも、劇的効果を一切排除。
「暗→明」の転換が、演出でなく、自然に満ち溢れるものとして描かれる。
フィナーレにはある種の「軽み」さえ感じられる。
「軽薄さ」の「軽さ」ではもちろんなく、芭蕉の俳諧に置けるそれ、と言ったら大仰だろうか。
汗を飛び散らかした「勝利の凱歌」というよりも、どこまでも健やかな「喜びの歌」。
弦の旋回、FI.やPiccのオブリガートの身のこなし、音の粒立ちにそれがはっきりと見える。
何度聞いても飽きない5番、と言える。
一度聴いて(いい意味で)グッタリする演奏にこそ(フルトヴェングラーのドラマやクライバーの緊張感)この曲の真骨頂はあるとは言え、滋味に溢れたこの演奏も素晴らしいと思う。
久々復活、「もっとベートーヴェン交響曲全集」(爆)。
とりあえず昨年末に「第9三昧」で聴いた盤は完結させねば、てことでケンペ(次はコンヴィチュニーの予定)。
まずは1番。
1楽章の冒頭の1音から澄み渡った空気が支配。
特別なことをするのではなく、ただ誠実に音を紡いでいく。
青春の息吹きや若々しさが「現在進行形」として表出されるのではなく、老成した大人がじっくりと回顧するような感じ……と言えばいいだろうか。
例えば終楽章の主部への入りで丁寧に弾き込まれる弦。
若さや熱気を過剰に強調することなく、落ち着いた身振りなのが清々しい。
ベートーヴェンに限らず、他の作曲家の曲でもそうなのだけど、ケンペは出自(オーボエ奏者)ゆえか、常に木管が美しい。
この曲でも明るくサウンドする管楽器が印象的。
そして5番。
1楽章では乾いた響きの、ザクザクした肌触りに驚かされる。
運命動機の2回目のフェルマータを気持ちデクレッシェンドさせる技。
その中で引き立つオーボエのソロのたおやかさ(ここでも木管だ!)。
運命動機の2回目の後に、「慣例」のパウゼを置かないことによる切迫感。
2楽章、背後の低弦や管楽器の刻みがしっかりと弾き(吹き)こまれているのに感心。
とにかく清潔な佇まいに、聴いているこちらもシャンとする。
結尾のゆったりとした納め方がロマンティック……だけど漂う「懐かしさ」。
スケルツォはじっくりと進め、決して煽らない。
この楽章に内在する「ユーモア」を敢えて強調しない。
ひたすらまじめに向き合う。
当然、3~4楽章間のブリッジも、劇的効果を一切排除。
「暗→明」の転換が、演出でなく、自然に満ち溢れるものとして描かれる。
フィナーレにはある種の「軽み」さえ感じられる。
「軽薄さ」の「軽さ」ではもちろんなく、芭蕉の俳諧に置けるそれ、と言ったら大仰だろうか。
汗を飛び散らかした「勝利の凱歌」というよりも、どこまでも健やかな「喜びの歌」。
弦の旋回、FI.やPiccのオブリガートの身のこなし、音の粒立ちにそれがはっきりと見える。
何度聞いても飽きない5番、と言える。
一度聴いて(いい意味で)グッタリする演奏にこそ(フルトヴェングラーのドラマやクライバーの緊張感)この曲の真骨頂はあるとは言え、滋味に溢れたこの演奏も素晴らしいと思う。
通勤ミュージック~090516 ― 2009/05/16 23:10:42
*ベートーヴェン:交響曲第2番・第4番(ケンペ/ミュンヘンpo)
第2弾は偶数曲集。
ステレオタイプな(笑)分類なら、端正・女性的とされる2曲。
当然ながらケンペは両曲とも、そう言った側面よりも、もっと質実剛健な感じを前面に出して解釈する。
2番のこの上もない健やかさ。
立ち上がる音が全て、見通しよく響き渡る。
淀んだところのない、澄んだ木管のハーモニー。
例えば2楽章のCl.のトリル。
ほんのりと暖かいサウンド。
テンポも穏やかで、まるで小春日和のよう。
ところが3楽章で一転。
キビキビとした速めのテンポ。
心地よい緊張感に、単に春風駘蕩だけで終わらせないぞ、という強い意志を感じる。
とは言え、決して聴き手を苦しくさせないのがさすが。
終楽章はじっくりと腰を据えて進む。
初期の曲としては重い(or古い)という声もあるかもしれないけど、ひとつひとつの音譜を慈しむような手触りが良い。
4番も同路線。
ゆっくりと歩を進める1楽章の序奏。
不安感や生成感よりもむしろ、音の動きを噛みしめながら確認するような感じ。
そして始まる主部。
辺りを払うかのような風格に、「大人(たいじん)」という言葉が頭をよぎる。
しかし決して威圧的でなく、どこか優しさを兼ね備えている。
2番と同じく、またまた意志的な3楽章。
他の楽章との差があるだけに、よけいに爽快。
終楽章は当然、クライバー・ムラヴィンスキー路線とは対極。
ドキドキするようなスリリングさとは無縁だけど、木管の掛け合いがしっかりと手に取るように紡がれていく。
第2弾は偶数曲集。
ステレオタイプな(笑)分類なら、端正・女性的とされる2曲。
当然ながらケンペは両曲とも、そう言った側面よりも、もっと質実剛健な感じを前面に出して解釈する。
2番のこの上もない健やかさ。
立ち上がる音が全て、見通しよく響き渡る。
淀んだところのない、澄んだ木管のハーモニー。
例えば2楽章のCl.のトリル。
ほんのりと暖かいサウンド。
テンポも穏やかで、まるで小春日和のよう。
ところが3楽章で一転。
キビキビとした速めのテンポ。
心地よい緊張感に、単に春風駘蕩だけで終わらせないぞ、という強い意志を感じる。
とは言え、決して聴き手を苦しくさせないのがさすが。
終楽章はじっくりと腰を据えて進む。
初期の曲としては重い(or古い)という声もあるかもしれないけど、ひとつひとつの音譜を慈しむような手触りが良い。
4番も同路線。
ゆっくりと歩を進める1楽章の序奏。
不安感や生成感よりもむしろ、音の動きを噛みしめながら確認するような感じ。
そして始まる主部。
辺りを払うかのような風格に、「大人(たいじん)」という言葉が頭をよぎる。
しかし決して威圧的でなく、どこか優しさを兼ね備えている。
2番と同じく、またまた意志的な3楽章。
他の楽章との差があるだけに、よけいに爽快。
終楽章は当然、クライバー・ムラヴィンスキー路線とは対極。
ドキドキするようなスリリングさとは無縁だけど、木管の掛け合いがしっかりと手に取るように紡がれていく。
通勤ミュージック~090521 ― 2009/05/21 23:47:08
*ベートーヴェン:交響曲第3番・「プロメテウスの創造物」序曲・「エグモント」序曲(ケンペ/ミュンヘンpo)
いよいよエロイカ。
個人的にはベートーヴェンの交響曲で一番好きだし、人生で一番最初に聴いた交響曲でもある。
また、あくまで主観だけど、ベートーヴェンの交響曲の中で一番演奏解釈が難しいのでは、と感じてる(第九よりも)。
素材を凝縮させるのではなく、拡大していくことによってもたらされるスケール感と、「飛躍」の交響曲でありながら、随所に見える対位法やバロック的な処理をどう両立させるか。
もっと簡単に言えば、アポロンとデュオニソスの両立しうる曲を、どう料理するか。
ケンペは、もちろん過度にドラマを強調することはしないけれど、これまで聴いてきた4曲とはひと味違って、爽やかな中にもキビキビとした運動性を前面に出してる。
しっとりと響かせる冒頭の2音にこそ、これまで同様の「大人」感は残っているけれど、勢い込んだTp.や、恒例の木管強調による隈取りが、この曲の「新しさ」を自然と意識させる。
ドラマより「うた」を意識させる1楽章でも、そのしなやかな若さが心地よく、曲想にフィットしていて心地よい。
とは言え、さすがは巨匠、展開部途中の弦の刻み(280~284)でテンポを心持ち落としたり、コーダのTp.はもちろん旋律なぞりだったりと、ツボを押さえてくれるのもまた快感。
……これまたあくまで主観だけど、コーダのTp.なぞりは、「改変」ではなく「教養」に近いとボク自身は考えている。
完全古楽器のピリオド解釈ならいざ知らず、モダン楽器なら(そこにピリオド解釈を反映させていても)ここの4小節でテーマを吹き鳴らすことは、ちっとも恥ずかしくないと思うのだけど。
閑話休題。
一つだけ惜しいのが、再現部直前のHr.のソロ。
あまりに音量を抑えすぎて、音が痩せてしまっていること。
ていうか、1楽章は全体的にもっとHr.きかせてもいいなぁと感じる。
2楽章は非常に端正。
大見得や大泣きとは無縁の、ノーブルな解釈。
Timp.の打ち込みも、柔らかめのマレットで、決して突出しない。
そのため、若干食い足りないというか、薄味に感じなくもないけれど、一種の形式美というか、一本筋の通ったものがある。
そして当然のことながら、この楽章で活躍するOb.の透明感!
ホントにケンペは木管の人、だなぁとつくづく思う。
スケルツォは、Hr.がふんわりと美しく鳴っていて嬉しい。
ていうか、この楽章(のしかもトリオ)でHr.ダメだったら致命的なんだけど。(笑
がなったりしなくても、力感たっぷりのTimp.や低弦の懸命な弾きっぷりも◎。
溢れ出す気持ちをぶつけるような終楽章冒頭。
パッサカリア主題の呼応は常にくっきりしていて、呼び交わしや追いかけ合いの中でも、決して混濁したり埋没したりしない。
旋律主題を吹くOb.の澄んだ明るさ!(またか、と笑われるかもしれないけど)
211小節目からの転調する、疾風怒濤のような変奏の部分、ここがボクはホントに大好きで、はっきり言ってここを聴くためにエロイカを聴くと言っても大げさじゃないくらいスキ。(笑
ケンペは無我夢中、という感じでないのは想定通りだけど、フォルムを崩さない中で厳しい力感と迫力を見せていて満足。
音階で駆け上がるCl.が刻印されるように浮かび上がっているのも良い。
他の変奏でも、歌うべきところではしなやかに(艶っぽくはないけれど)、ピシッと決めるところでは厳しさを押しだし、変奏曲が陥りがちな散漫さからは無縁。
何より、流れずにキチッと弾いている弦の刻みが、この楽章(というか全曲か?)に一本芯を通している。
あとやっぱり、くどいけど木管。
最後の最後でもCl.の音階をしっかりと聴かせ、キチッとしたフォルムにある種の明るさという色を添えている。
フィルアップの序曲のうち、「プロメテウス」は小振りというか、若干肩の力を抜いた感じ。
「エグモント」は劇性を強調するよりも、抑えた筆致で、例えば冒頭の音圧も刺激的ではない。
主部に入ってからも、グッと思いを噛みしめながら、悩みつつ歩む人のような進行。
派手な隈取りはなくとも、それゆえにコーダの転調が空騒ぎではない本当の解決として響いてくる。
いよいよエロイカ。
個人的にはベートーヴェンの交響曲で一番好きだし、人生で一番最初に聴いた交響曲でもある。
また、あくまで主観だけど、ベートーヴェンの交響曲の中で一番演奏解釈が難しいのでは、と感じてる(第九よりも)。
素材を凝縮させるのではなく、拡大していくことによってもたらされるスケール感と、「飛躍」の交響曲でありながら、随所に見える対位法やバロック的な処理をどう両立させるか。
もっと簡単に言えば、アポロンとデュオニソスの両立しうる曲を、どう料理するか。
ケンペは、もちろん過度にドラマを強調することはしないけれど、これまで聴いてきた4曲とはひと味違って、爽やかな中にもキビキビとした運動性を前面に出してる。
しっとりと響かせる冒頭の2音にこそ、これまで同様の「大人」感は残っているけれど、勢い込んだTp.や、恒例の木管強調による隈取りが、この曲の「新しさ」を自然と意識させる。
ドラマより「うた」を意識させる1楽章でも、そのしなやかな若さが心地よく、曲想にフィットしていて心地よい。
とは言え、さすがは巨匠、展開部途中の弦の刻み(280~284)でテンポを心持ち落としたり、コーダのTp.はもちろん旋律なぞりだったりと、ツボを押さえてくれるのもまた快感。
……これまたあくまで主観だけど、コーダのTp.なぞりは、「改変」ではなく「教養」に近いとボク自身は考えている。
完全古楽器のピリオド解釈ならいざ知らず、モダン楽器なら(そこにピリオド解釈を反映させていても)ここの4小節でテーマを吹き鳴らすことは、ちっとも恥ずかしくないと思うのだけど。
閑話休題。
一つだけ惜しいのが、再現部直前のHr.のソロ。
あまりに音量を抑えすぎて、音が痩せてしまっていること。
ていうか、1楽章は全体的にもっとHr.きかせてもいいなぁと感じる。
2楽章は非常に端正。
大見得や大泣きとは無縁の、ノーブルな解釈。
Timp.の打ち込みも、柔らかめのマレットで、決して突出しない。
そのため、若干食い足りないというか、薄味に感じなくもないけれど、一種の形式美というか、一本筋の通ったものがある。
そして当然のことながら、この楽章で活躍するOb.の透明感!
ホントにケンペは木管の人、だなぁとつくづく思う。
スケルツォは、Hr.がふんわりと美しく鳴っていて嬉しい。
ていうか、この楽章(のしかもトリオ)でHr.ダメだったら致命的なんだけど。(笑
がなったりしなくても、力感たっぷりのTimp.や低弦の懸命な弾きっぷりも◎。
溢れ出す気持ちをぶつけるような終楽章冒頭。
パッサカリア主題の呼応は常にくっきりしていて、呼び交わしや追いかけ合いの中でも、決して混濁したり埋没したりしない。
旋律主題を吹くOb.の澄んだ明るさ!(またか、と笑われるかもしれないけど)
211小節目からの転調する、疾風怒濤のような変奏の部分、ここがボクはホントに大好きで、はっきり言ってここを聴くためにエロイカを聴くと言っても大げさじゃないくらいスキ。(笑
ケンペは無我夢中、という感じでないのは想定通りだけど、フォルムを崩さない中で厳しい力感と迫力を見せていて満足。
音階で駆け上がるCl.が刻印されるように浮かび上がっているのも良い。
他の変奏でも、歌うべきところではしなやかに(艶っぽくはないけれど)、ピシッと決めるところでは厳しさを押しだし、変奏曲が陥りがちな散漫さからは無縁。
何より、流れずにキチッと弾いている弦の刻みが、この楽章(というか全曲か?)に一本芯を通している。
あとやっぱり、くどいけど木管。
最後の最後でもCl.の音階をしっかりと聴かせ、キチッとしたフォルムにある種の明るさという色を添えている。
フィルアップの序曲のうち、「プロメテウス」は小振りというか、若干肩の力を抜いた感じ。
「エグモント」は劇性を強調するよりも、抑えた筆致で、例えば冒頭の音圧も刺激的ではない。
主部に入ってからも、グッと思いを噛みしめながら、悩みつつ歩む人のような進行。
派手な隈取りはなくとも、それゆえにコーダの転調が空騒ぎではない本当の解決として響いてくる。

最近のコメント